どこで受験勉強をしていますか?
勉強に集中したいのに気が散ってしまうのは、勉強する場所が自分に向いていないのかもしれません。
受験生が勉強に利用する場所の特徴などを紹介していきます。
合わせて、集中力が途切れやすいウチの娘が勉強している場所について、実際の状況を紹介して参考にしていただければと思います。
第10回までのストーリーの概略
・2022年7月、自称進学校で落ちこぼれていた高校2年生の娘が突然「私、東大、目指す」と宣言
・「東京大学 現役合格」と紙に書いて、自分の部屋に掲げて東大合格を目指し始める
・8月の終わりに東大本番模試で偏差値29.5のE判定で自分の現在地を否が応でも知る
・学校の進路希望調査で「東京大学志望」を提出し、自他ともに勉強するしかない状況に追い込まれる
・9月に勉強するために塾を探し始める
・「河合塾現役館」、「東進ハイスクール」、「武田塾」の無料体験を受ける
・10月下旬に「家から自転車10分で近くて通いやすい」、「参考書での自学自習の勉強法を身につけられる」、「逆転合格を目指す」の理由で武田塾に入塾
・武田塾に入塾してから、毎日のように武田塾へ自習しに行き、勉強習慣を身に付ける
・11月の東進ハイスクールの「全国統一高校生テスト」で偏差値35.9を記録
・2023年1月の「共通テスト同日体験受験」で900点満点中の397点、偏差値47.4
・2023年2月の「東大入試同日体験受験」で440点満点中の34点、偏差値27.6
・武田塾の参考書ルートや勉強スケジュールの指導により、勉強習慣が身につき自学自習できるようになったことから、2023年2月いっぱいで武田塾を退塾
・武田塾を退塾後、学校や図書館、自宅で自学自習して受験勉強を継続中
・2023年6月に部活を引退し、勉強へのモチベーションがダウン、夏休み前になんとか回復
・2023年の夏休みに今までの遅れを取り戻すべく勉強に励んだが思ったより勉強に集中できず
・2023年9月に模試の結果を確認し、東大レベルに全く到達していないことを痛感
・2023年9月に東大合格を諦め、志望校を千葉大に変更
・2023年10月、受験勉強に向けてやる気の出る言葉を家中に貼った

⇓⇓⇓ 夜更かし朝寝坊の受験生も「ポイント制お小遣い」で良い習慣を身に付ける! ⇓⇓⇓

この記事は、埼玉県の県立高校の自称進学校に通う娘が、東京大学の受験へ向けてのストーリーでしたが、2023年9月に東大合格レベルの到達不可能と判断し、志望校を千葉大学へ変更して千葉大の受験へ向けてのストーリーとなっています。。
今回はメソッド編として、塾に通っていない娘が勉強する場所は?
について紹介していきます。
以降は都度、記事をアップしていき、2024年3月の大学受験合格発表までのストーリーをお届けしていく予定です。
ちなみに東京大学合格体験記ではありません。
千葉大学合格体験記でもありません。
実際にどの大学に合格し入学するのかは、現時点では分かりません。
あくまで東大目指してからの千葉大志望へ変わった受験生の体験談ですので、ご理解のほどよろしくお願いします。
大学受験をしている高校生やその保護者の方の参考になれば幸いです。
娘のプロフィール(2022年7月東京大学を目指し始めた時点)
・埼玉県の県立高校(自称進学校:偏差値60代)に通っている
・学校での定期テストの順位は1年の頃から320位前後(約350人中)
・英語が苦手で数学が比較的に得意
・塾に通っていない
・学校の課題の未提出がたまにある
・水泳部に所属
・高校受験で燃え尽きて勉強へのやる気が全く見られない
・勉強習慣が全くできていない
・いつもスマホをいじって、手放せない
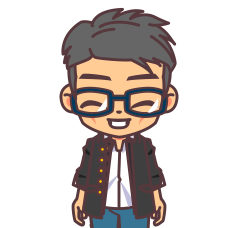
父親の僕自身は娘の大学受験へ向けての勉強を通じて大学受験について研究を始めました。
大学受験の研究が楽しくなって娘のために情報を調べてあげたりと、娘の受験勉強を応援している立場です。
まずは14日間の無料体験をしてみませんか?(期間中に解約すれば無料)
↓↓↓スタディサプリ公式サイトはこちら↓↓↓
受験生にとって勉強する場所(環境)は大事
受験生にとって、勉強する場所は重要な要素のひとつです。
勉強する場所によって、集中力やモチベーション、効率が変わってきます。
人はすぐにサボりたくなる生き物
もともと人間の脳は面倒くさがりで考えることが嫌いです。
勉強習慣が身に付いていない人にとって勉強をすることは、面倒なことになります。
なので、自分が決めた通りに勉強ができなくても「自分はすぐにサボってダメな人間だ」とは考えないでください。
キングコングの西野亮廣さんが物事がうまくいかない原因は、「ヒューマンエラー(人間のミス)」はなく「システムエラー(仕組みが悪い)」が全てだと言っていました。
勉強できない個人の責任ではなく、勉強をするための仕組みづくりに問題があったということです。
勉強する場所は勉強するための仕組みの重要要素ということになります。
人によって集中しやすい場所は違う
・静かな場所の方が集中しやすい人
図書館、塾の自習室など
・多少の雑音がある方が集中しやすい人
カフェ、フードコート、学校、電車の席
・周りの目があった方が集中しやすい人
図書館、塾の自習室、学校
・一人きりの部屋の方が集中しやすい人
自分の部屋、個室レンタルスペース
集中しやすい環境作りが大事
人は誘惑に非常に弱いです。
受験勉強の時間を奪う一番はやはりスマホでしょう。
スマホには魅力的なコンテンツがあり、人々の時間を奪うように巧みに設計されています。
自分の意志の強さで抗うことは基本的に不可能と思った方が良いでしょう。
スマホに勉強時間を奪われないためには、
・勉強場所にスマホを持ち込まない
・人に預ける
・監視されている状況を作為する
・スマホロックタイマーなどを活用する
などのスマホをいじることができない環境を整えてから勉強をはじめましょう。
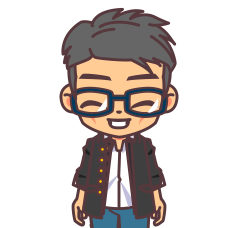
ウチの娘もスマホの誘惑に勝てず勉強時間を奪われ続けています。
そこで、時間を設定したらその間はスマホをいじることができない、スマホ用の携帯ロックボックスを購入しました。
勉強する場所のそれぞれの特徴
勉強する場所のそれぞれの特徴を紹介します。
学校
学校の特徴は次のとおりです。
・大学受験をする仲間がいるので刺激を受ける
・学校の先生がいるので分からない箇所を聞くことができる
・多少の雑音がある
・周りの目がある
・友達に聞くことができる
・友達とおしゃべりが長くなってしまう場合がある
・学校が開いている時間しか利用できない
・学校の日は朝7時くらいから勉強できる
授業前に1時間の勉強は効果大
理想的な学校の利用方法としては、朝早く起きて、学校が開くのと同時に学校に入って図書室などの静かなところで朝のホームルーム前まで集中して勉強する。
放課後、すぐに勉強を始めて最終下校時刻のギリギリまで勉強する。
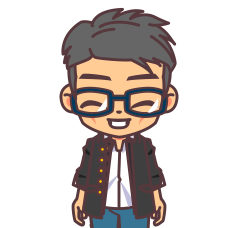
塾に行っていない人の学校の日の勉強法としては無駄な移動もなく、最適なパターンと言えるでしょう。
塾や予備校の自習室
塾や予備校の自習室の特徴は次のとおりです。
・大学受験をする仲間がいるので刺激を受ける
・塾講師がいるので分からない箇所を聞くことができる
・静か
・周りの目がある
・参考書などが置いてある
・夜遅くまでやっている場合が多い(22時くらいまで)
・朝は10時くらい利用可能の場合が多い
・その塾や予備校に通っていないと利用できない。
当たり前ですが、受験勉強するのに最適な場所と言えます。
弱点としては塾や予備校に通っていないと利用できない点と早朝に利用できない場所が多いところでしょう。
カフェ・フードコート
カフェ・フードコートの特徴は次のとおりです。
・飲み物を飲んだり食べ物を食べることができる
・周りの雑音がある
・勉強していると注意される場合がある
・人の動きがある
・飲食代金がかかる
人によってはある程度の雑音があった方が集中できる人がいるようです。
そのタイプの人には向いている場所と言えるでしょう。
注意点としては、勉強する場所として提供されている訳ではないので、混雑具合やお店の状況(勉強利用を禁止など)を確認し、迷惑とならないようにする配慮が必要です。
筑横千専門塾|筑横千まで鬼管理する塾への無料説明会の申込⇑⇑⇑ 筑波大学、横浜国立大学、千葉大学に特化した対策で徹底管理して合格率74%の塾
受験生の娘が勉強するのに実際に利用している場所は?
ウチの娘が実際に勉強するのに利用している場所やその状況を紹介します。
大学受験を目指す仲間がいる学校で勉強する
ウチの娘が一番勉強に集中できるのは学校となります。
授業が終わったあとにそのまま残って勉強するので移動する手間もないのも良いですよね。
やはり大学受験を目指す仲間が勉強しているのは刺激になります。
当初は自分の教室の机で勉強していたのですが、慣れてくるとサボってしまうようになったようです。
娘が通っている高校では廊下に勉強するための机が並べてあるのですが、そこですと周りに監視されている感じがしてサボりにくくなり、勉強に集中できるようになったようです。
土日などの休みの日でも娘の通う学校は開放しているので、休みも学校へ行って勉強することも多いですね。
静かで他にも勉強している人がいる図書館で勉強する
図書館でもよく勉強をしています。
ウチの近所の図書館は平日は夜9時30分までやっているので、学校から早めに帰ってきた時に利用しています。
また、休日は学校ではなく図書館へ行くことも多いです。
図書館は静かなのが良いですし、他にも勉強している人がいるのが刺激になるようです。
自宅から自転車で5分くらいなので、近いので便利ですね。
家だと勉強に集中できない時は、図書館に向かうようにしています。
休館日があるのと、土日祝日は5時までなので、曜日や時間を考えて利用する必要があります。
自宅で勉強する
学校や図書館で勉強できない日や家から出るのが面倒になった時に自宅で勉強しています。
多くの人が言っているように、自宅で勉強に集中するのはウチの娘も難しいようです。
自宅に勉強専用のスペースを設けていますが、始めるまでに時間を要してしまうことが多いですし、始めてもすぐに集中力が途切れてしまうことが多いですね。
娘にとっては親では監視の目にはならないようです。
気分を変えて喫茶店・フードコートで勉強する
図書館がやっていない時にたまに近所のマックやイオンのフードコートなどで勉強することがあります。
気分転換がてらに勉強する場所を変えて自分なりに工夫をしているようです。
たまに中学時代の友達と一緒に勉強する場合も近所のマックなどを利用しています。
軽い食事や飲み物があって、たまにおしゃべりをしながら勉強するには、ファーストフード店やフードコートなどが良いかもしれませんね。
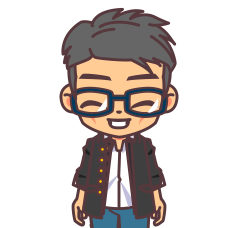
友達と勉強して勉強が効率が良いかどうかは微妙だと思いますが、友達との交流も大切ですよね。
受験生の勉強スケジュールを管理できる神アプリ!受験勉強を頑張る仲間の刺激も感じれる↓↓↓
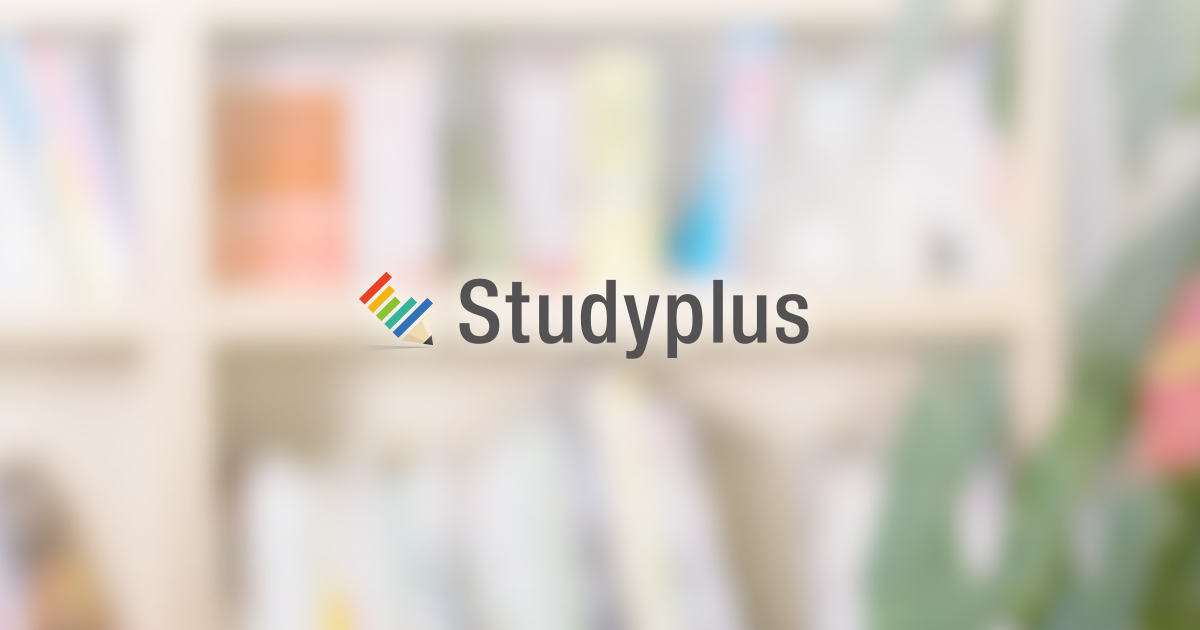
勉強する場所のパターン化が重要
今日はどこで勉強しようかな?
などと毎日のように考えている人はいませんか?
毎回勉強する場所を都度考えて決めていると脳はそれだけで疲れてしまい、勉強が面倒になりかねません。
あらかじめ勉強する場所のパターンを決めておき、考えることもなくその場所で勉強を開始するようにしましょう。
例えば学校がある日は、授業終了後、学校で勉強し、学校がない日は図書館で勉強する。
学校や図書館が利用できない時は、自宅で勉強する。
といったように基本パターンを決めて淡々とそのパターン通りに勉強すると勉強習慣が身につきやすいです。
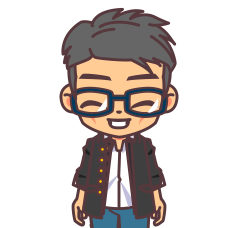
ウチの娘も毎日のようにどこで勉強をするのかを考えて、勉強を始めるのが遅くなっていることが多い気がします。
パターン化して、余計なことを考えずに勉強を始めるようにアドバイスしています。
まずは14日間の無料体験をしてみませんか?(期間中に解約すれば無料)
↓↓↓スタディサプリ公式サイトはこちら↓↓↓
まとめ
受験勉強をする場所は、自分にとって集中しやすい環境を選ぶことが大切です。
学校、塾、図書館、自宅、カフェなど、それぞれの場所にはメリットとデメリットがあります。
自分のタイプに合わせて、勉強する場所のパターンを決めておくと、勉強習慣が身につきやすくなります。
例えば、学校は仲間と刺激し合える場所ですが、学校が開いている時間しか利用できません。
塾は受験生に最適な場所ですが、早朝に利用できない場合が多いです。
図書館は静かで他の勉強者もいる場所ですが、休館日や利用時間に制限があります。
自宅は移動しなくて良い場所ですが、誘惑が多くリラックスし過ぎに注意が必要です。
ウチの娘の場合は学校を主体に図書館を併用して勉強し、それ以外は基本は自宅で勉強するというスタイルで勉強しています。
塾は行っていません(高3の10月時点)が、自分の予定に合わせて柔軟に勉強をする場所を決めています。
このように、勉強する場所によって集中力やモチベーション、効率が変わってきます。
自分の性格や行動に合わせて、最適な勉強する場所を見つけてください。
あなたの受験勉強を応援しています!
⇓⇓⇓合わせて読みたい⇓⇓⇓
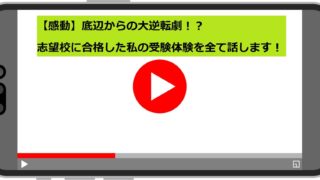
↓↓↓スタディサプリ大学受験講座でお得に成績アップ!料金と効果解説↓↓↓






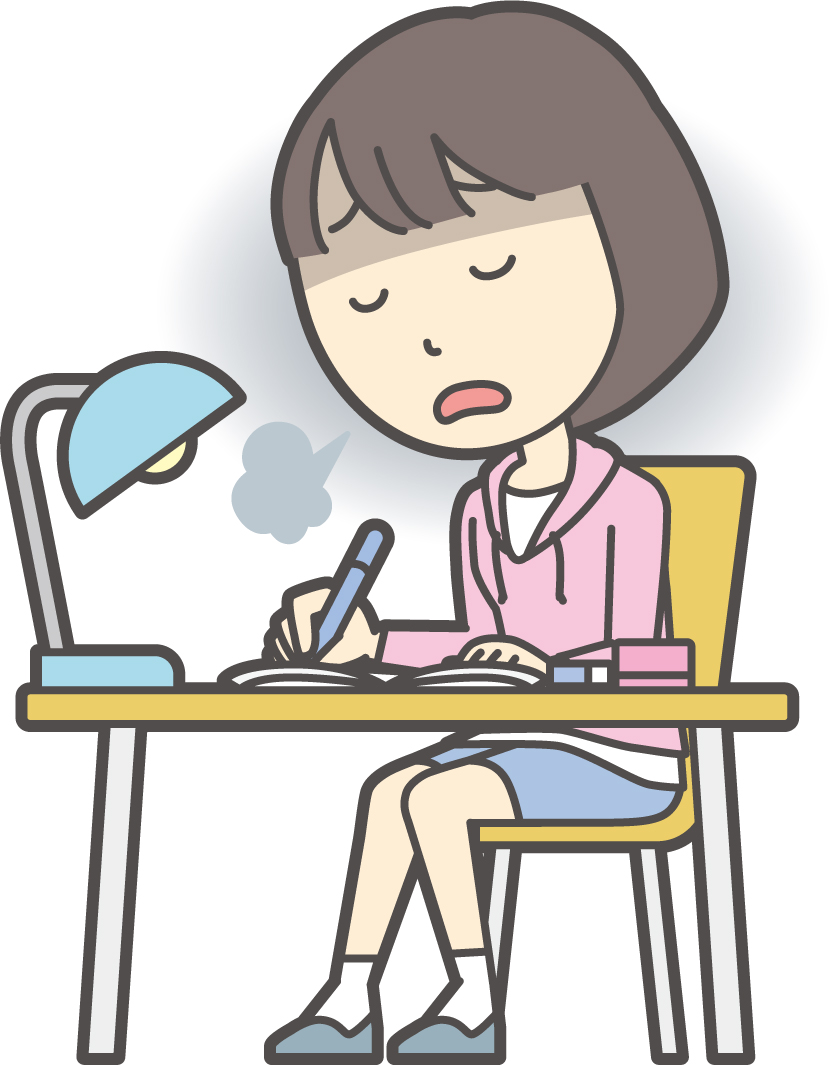
コメント